本紙6・7ページの「母ゴコロ横丁」に並んでいる、何気ない子育ての記事。だがこれが、どれほどの価値を持つキラーコンテンツかは、わかる人にしかわからない。いや、わかる人にはわかる。
見栄を張った記事もなければ、映える写真もない。お母さん記者はペンを持ち、母である自分に向き合うことで心を落ち着かせる。さらに読んでくれたお母さんが共感すると、つながる喜びを感じることができる。
入稿前には、お母さん記者に掲載許可と原稿確認をお願いする。あるお母さんから「すみません。わが子から掲載許可が下りなくて、ごめんなさい」と返事があった。掲載できないのは残念だが、子どもが母の記事を読んでくれているのだと、ちょっとうれしくなった。
同時にちょっぴり不安を感じた。本来、記事は読まれることを意識して書くものだが、母ゴコロの記事は少し違う。意識するとすれば、内なる母ゴコロだけ。読者を意識しないところに価値がある。もちろん日記ではないから、無意識の中での意識はある。それこそ、お母さん大学流のマザージャーナリズムだ。
子どもが思春期を迎えるあたりで、お母さんがペンを持てなくなることは想定内。だがITの普及でそれが低年齢化している。これからは、わが子が読むことを意識してペンを持たなければならないのだろうか。お母さん業界新聞は実名発信だから、検索も容易い。「掲載しないで」と言う、子どもゴコロもわからないでもない。
子どもが小さい頃は、反対のケースが多い。新聞が届くと、子どもたちは我先にと封を開け、新聞を広げて記事を探す。お母さんが書いた(自分のことが書かれた)記事がないと、チェッと舌打ち。「お母さん、今月宿題しなかったの?」と叱られるのは、母のほうだ。
思春期を過ぎると、母の記事を余裕で眺め、一笑に付したり、こう書けばとアドバイスをくれたりする子どももいる。だが、その日まで記事を書くお母さんも、絶滅危惧種といえそうだ。地球環境の悪化で、多くの生物たちを心配していたが、「お母さん業界新聞」も絶滅危惧種。もはや他人事ではなかった。
子どもたちには、なぜ母ゴコロの記事を書くのか。その記事は、家族の宝になるだけでなく、地球の未来にも関係するものだと伝えるしかないか…。いや、それも、大人の都合を押し付けているようで好まない。
この問題を解決するまでは、なんとか新聞を存続させなければ。お母さんが絶滅危惧種にならないようにするためにも。
(藤本裕子)
お母さん業界新聞 コラム百万母力
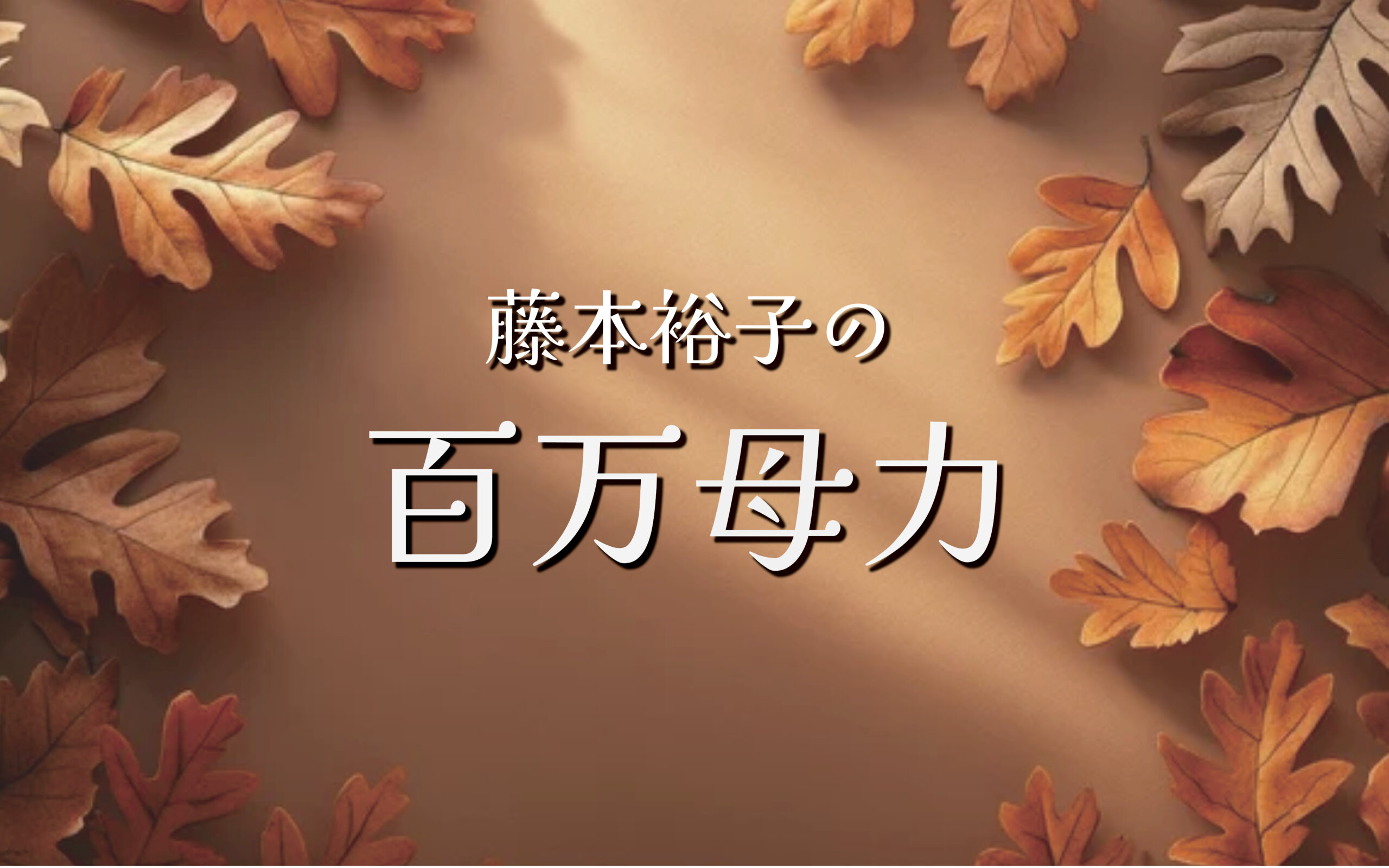


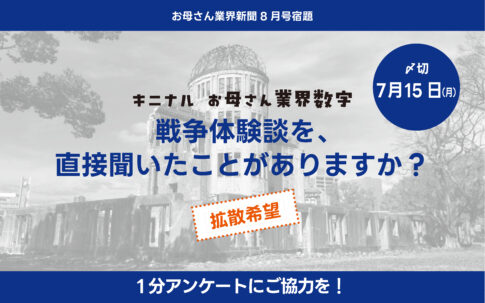

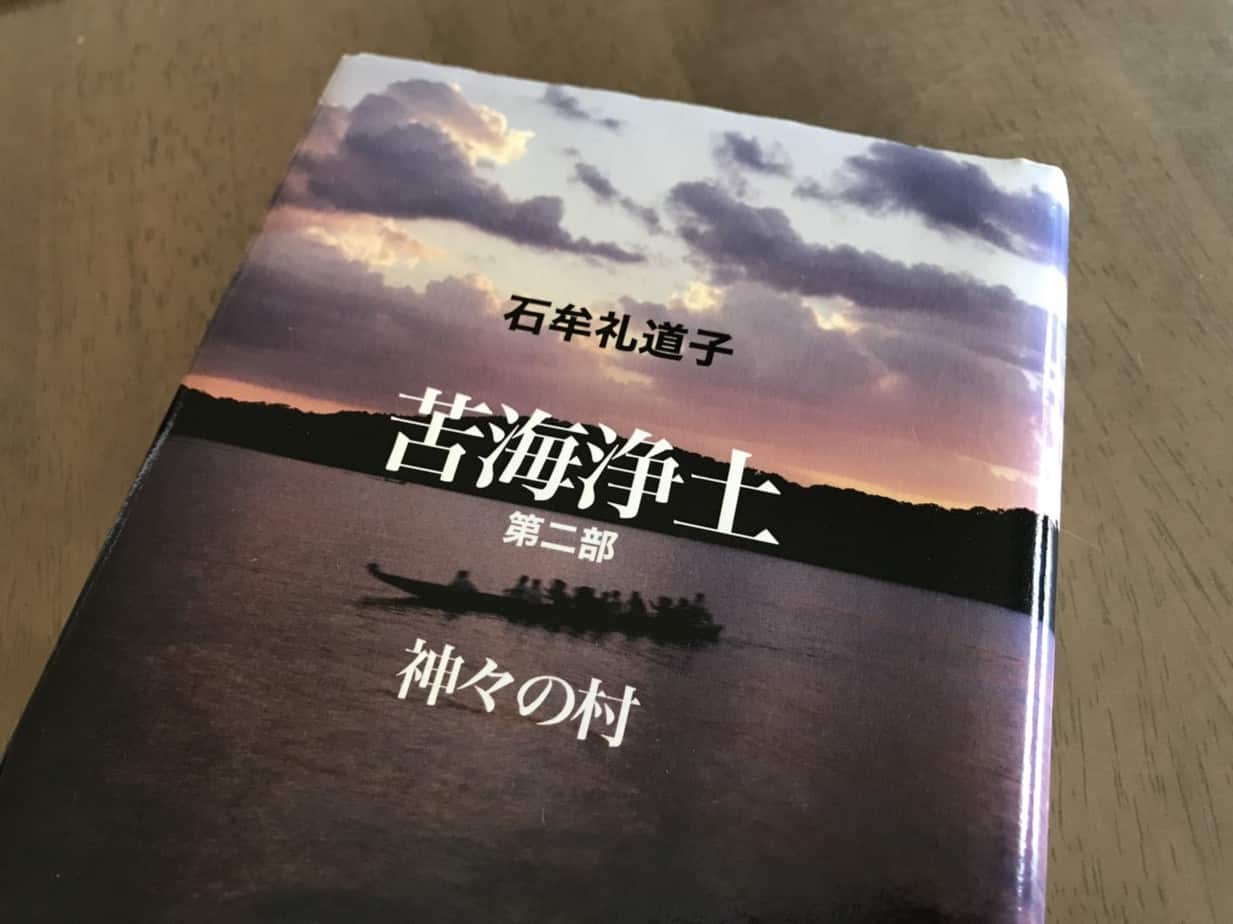

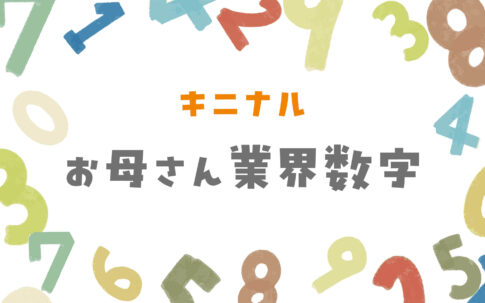



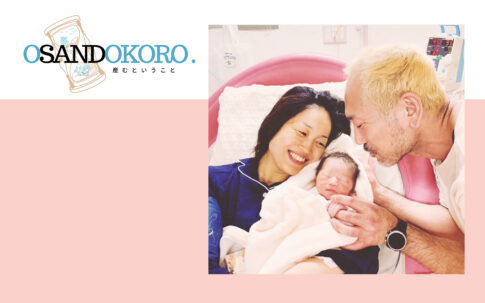
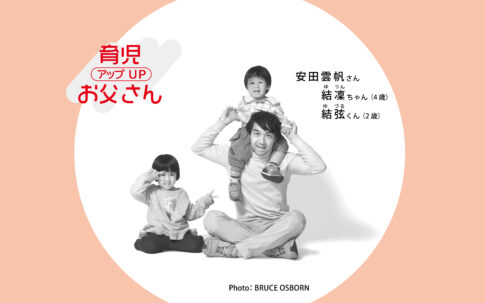



















今の20代30代は、子供の顔や名前はSNSには絶対に載せない!という意識のママさんが多いので…物騒な世の中になっている分危機感を持って写真を扱う親が多い印象です。
私も元はそちら側なので、いつまで続けようか、写真を後ろ姿や雰囲気だけにするかなどずっと考えています。