以前からお世話になっている、奈良市在住のОさんから、メールが届いた。「おんぶ紐の件、その後どうなっていますか?」とあり、思い出す。
生前、洋裁をされていたOさんのお母様が遺した布で、「おんぶ紐」をつくれないかと、ずいぶん前に相談されていたが、何も動いていなかった。余裕がなくて、ごめんなさい…。
おんぶ紐…。最近は抱っこのお母さん(お父さんも増えたが)ばかりで、おんぶしている人をあまり見かけない。
昭和の時代に子育てをした私は、「おんぶ派」だった。娘が3人いたため、スーパーに行く時は、背中に1人、自転車の前と後ろに1人ずつ。プラス買い物袋だから、母は強し。若い頃は、私もたくましい母だったのだろう。
当時から「抱っこ紐」の存在はあった。だがおんぶのほうが、家事はできるし、子どもの体が背中にフィットして、私には心地よかった。ただ、胸のばってん姿は、正直イヤだった。
本紙の表紙企画「母たちへの一文」を授けてくれた、故直木賞作家の水上勉氏は、幼い頃、目が不自由な祖母の背中で、世の中の不条理を見たという。
「共視」というが、母の背中越しに、母と同じ目線で社会を見ることができる。子どもながらに、祖母の背中を通して感じた人間の卑しさや醜さ…それらすべてが自身の小説に根づいていると語っていた。
偶然にも、Оさんからメールをもらった翌日のこと。小雀五霊社(横浜市戸塚区)のお祭りで、「ハハコモマイ・だっこフラ」を披露する機会をいただいた(3頁)。
格式ある神社の神楽殿という荘厳な舞台。笑顔でフラを踊るお母さんの胸で、すやすやと眠る赤ちゃんたち。
会場がやさしくあたたかな空気で満たされたところで、続いては、フラの主宰・小林順子さんのソロステージ。平和への祈りを込めた渾身の舞いは、静かに、力強く
会場を包み込んだ。
すると、なぜかその瞬間、Oさんのお母様が遺されたという布たちが、私の脳裏に浮かんできた。
しかも今月末、別件で奈良に行く予定があったという偶然。
母たちの舞いに魅せられた五霊社の神様が、ハワイと奈良の神々を引き寄せたのか。いや、縁日のビールに浮かされた、私の妄想かもしれないけれど…。
ここで問題だ。おんぶ紐をつくるだけなら、誰にでもできる。私たちがやるなら、意味あるものにしなければ。
布たちが、未来の母たちのために出番を待っている。枯れそうな私のスイッチを母モード「強」にした。
(藤本裕子)
お母さん業界新聞10月号





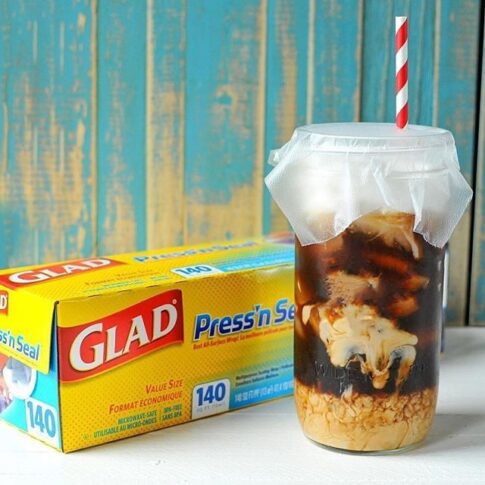


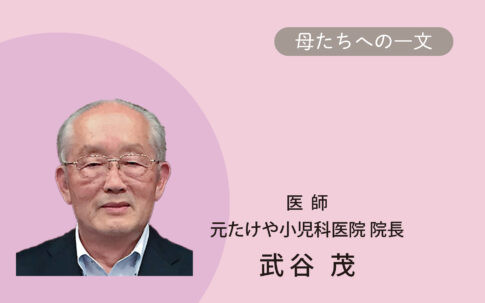

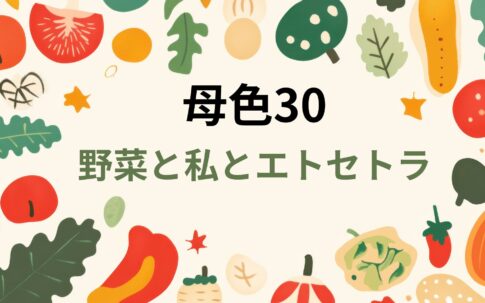

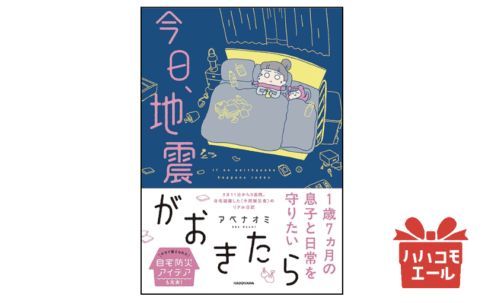




















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。