家の整理をしていたら、懐かしいものが見つかった。40年前に書いた「赤ちゃん日記」。私の初めての育児日記である。恐る恐る開いてみると、案の定、三日坊主。いや、六か月坊主だった。しかも、これしか書けないのかーというほど、お粗末な内容である。
○月×日。生まれて4日目。お母ちゃんは少し疲れてきました。それは、あなたが夜眠ってくれないからです。毎晩、2~3時間の睡眠。しんどい。でも、あなたのかわいい顔を見ていると、なんともない。
○月▽日。お乳を飲むとき、おっぱいをひっぱって、顔を真っ赤にして怒る。今日も寝てくれない。けれど、かわいい。
○月◇日。昼間は全く寝ない。夜中まで起きていて、
抱っこするとご機嫌だけど、寝かすとすぐに泣く。もうクタクタの毎日。でも、本当にかわいくてたまらない。
眠れなくて辛い。でもかわいい。と、ただそれだけしか書いていない。表現力も感性もない文章だ。お母さん大学では、半径3メートルの世界に未来があると伝えているが、私の日記は、半径30センチメートルにも満たない世界である。
それに比べると、お母さん大学のお母さんたちが綴る記事の、なんと素晴らしいことか。それぞれの半径3メートルの世界が、ドラマのシーンでも見ているかのようにまざまざと浮かび上がる。
日記とお母さん大学の記事の違いは明らかだ。それは、読み手の誰かを意識すること。だからといって、かっこつけるわけではなく、無意識の中に「母ゴコロ」という意識が存在している。それが、お母さん大学が提唱するマザージャーナリズムなのだ。
11月は、児童虐待防止推進月間である。お母さんたちの書く記事が、どこかの町で、孤独な子育てをしているお母さんに届けば、「あ、私と同じ!」と、ほっこり笑顔が広がるだろう。
それだけではない。その記事たちが、何十年後かに、再び宝石のように輝く時が来る。子どもが母から巣立つ時、人生の岐路に立った時、命を感じるほどの出来事があった時。そして、母である最期を迎える時も。
母ゴコロの記事は、どんな時も、書く人の心に寄り添ってくれるのだ。
決して、あの日には戻れない。今、私にできることは、お母さんたちが安心してペンを持てる場を守ること。
毎日、お母さんたちの記事を読んでほっこり。遠いあの日に思いを馳せている。
(藤本裕子)
お母さん業界新聞11月号 百万母力




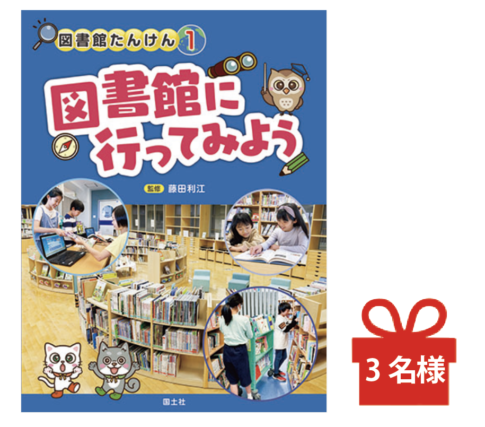





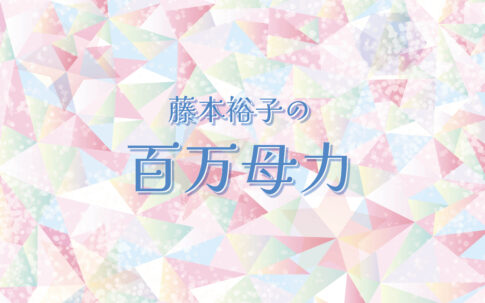
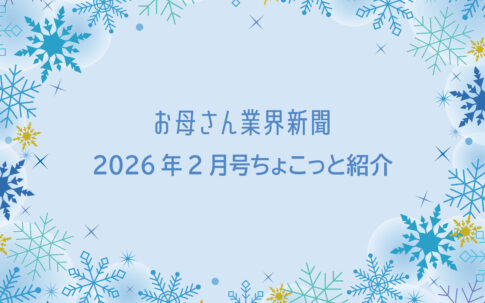

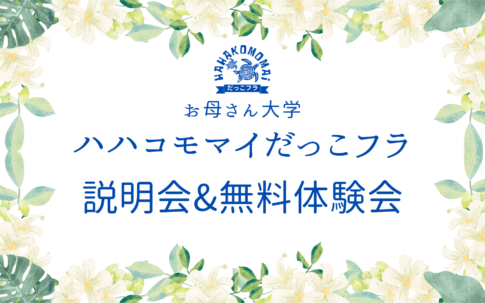



















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。