9月19日、お母さん業界新聞社の編集部があるワーホプレイスとらんたんに、早稲田大学英字新聞会「ザ・ワセダ・ガーディアン」の皆さんが来所した。「お母さん業界新聞」のお母さん記者を取材したいとのこと。テーマは「お母さん業界新聞」と「受験期の子どもをサポートする親の気持ち」について。担当したのは本部スタッフの植地宏美。わが子と同年代の学生から取材を受けることで、改めて母とは何かを考えさせられたと植地。さて、その植地宏美とはどんな母なのか。それは、お母さん大学サイトに書かれている記事を見ればわかる。母歴となる記事も同時に読んでほしい。(編集部)

ついインタビューをしてしまう
母になって23年。お母さん記者歴は15年。年齢とともに加速する図々しさも相まって、ついつい逆インタビューをしてしまう。
「どうしてこのサークルに入っているの?」「将来は記事制作経験を活かせる仕事に就きたい?」と先攻質問。わが子と同年代の学生さんに、質問することはあってもされることはない。
「お母さん業界新聞に携わっているのはなぜですか?」と聞かれ、思考が止まる。「お母さんだから」という言葉で済ませてはいけない気がしたのだ。言葉を選びながら、でもかっこつけずに、素直に答えるように心がけた。
学生とお母さん、いいね!
受験期の子どもとの関わり方を聞かれると、その時の感情が蘇った。子どもが成長していく過程では多かれ少なかれ「受験」の選択を迫られる。その選択をする頃は思春期や反抗期とも重なり、予想以上の試練が待っている。
将来を案じるがゆえ、口を出したくなるのが親。相反して、見えない未来への不安や友だちの選択との比較、部活と勉強の両立といった、さまざまな障害や誘惑に迷うわが子。
その後の一生を決定づけるくらい大切なものなのに、進路決定に与えられる時間は短い。
お互いの言い分も気持ちもわかっていながら、うまく伝えられない。この点において、私とインタビューする学生さんたちとは、親と子という逆の立場にもかかわらず、「共感」できた。
母から社会へバトンを渡す
子どもを育てるということは、未来をつくること。それは社会をつくることともイコールだ。35年以上孤育てをなくし、お母さんを笑顔にするために存在してきた「お母さん業界新聞」。
母が変われば、きっと社会も変わる。完璧ではないからこそ、語り合える。悩むからこそ共感が生まれる。お母さん記者が綴る「母ゴコロ」記事は、唯一無二の子育て共感記事といえる。
学生たちの質問の奥には、次世代の親たちへの眼差しを感じた。社会を変えるのは特別な誰かではなく、命がけで産んだわが子のために、半径3メートルの世界を感じる、フツーのお母さんに違いない。
将来、彼らが社会に出て、いつか親になった時。この日の話を思い出すかもしれないと思うと、母としての役目はまだまだ続いているのだと思った。
本部スタッフMJ・植地宏美
母ゴコロ記事2024.03
呼ばれた全ての名前にエールを
「不在でも、お子さんの名前を読み上げてもよろしいでしょうか?」3 日前、次男の担任の先生に言われた言葉。
次男はこの1 年間、ほとんど学校へ行かなかった。コロナ禍に突入した中学校生活。行事は延期に中止にマスクに制限に。もともと休みがちな彼には乗りこなせないものたちだった。
「お願いします」そう言って次の瞬間、ああそうか、私も卒業式に参加できないのか、と思った。
しかし年度末生まれ、末っ子次男の不思議な性質「チョウゼツマイペース」が発揮され、卒業式前日、登校した。そして彼は、卒業式にも出席した。半数以上がマスクをつけている中、彼はマスクはつけず、堂々としていた。
卒業証書授与の際、呼ばれるけど返事のない名前があった。きっと、その子たちは、今日来られなかった事情がある。みんな誰も、当たり前のように聞き流していくけど、私には苦しかった。その子たちのお母さんが、今どんな気持ちで家にいるのか、とてもよくわかるからだ。
自分の子どもの晴れ姿を見たくない親なんていない。でも子どもの気持ちを尊重してグッと我慢している。わからない、子を罵ってしまった人もいるかもしれない。不登校と呼ばれる子の親は、揺れる心と闘うしかないのだ。
大丈夫だよ。そんなお母さんたちに伝わるといいな。別にみんなと同じスタートラインに立つ必要なんてない。おはようって言えたらハッピー。いつか大きく羽ばたく日が来ると信じる。笑顔で過ごす。それしか、お母さんにはできない。
次男は進学しないことを選んだ。今は。帰宅して「自由になった気分」と言った。
今日、名前の呼ばれた250 名の卒業生たち、すべてにエールを贈ります。いらない人なんていない。私はあなたの名前をしっかり聞いたからね。卒業、おめでとう。

母ゴコロ記事2022.11
16回目の誕生日
長男の誕生日。何もできないから、お寿司でも買って帰ろうと思ってリクエストを聞いたら、「サーモン40貫」。
いやいや、さすがに食べられないでしょ、と思いながらも、30貫を買った。軍艦もいくつかあったが、案の定残した…。
ほらね。そんな16回目の誕生日。

母ゴコロ記事2025.06
子育て相対性理論
長男が大学生になった。高校生の頃は毎朝1時間かけて声がけして起こして、せっかくつくったお弁当も「今日食堂で食べるからいらない」と言われ、不貞腐れたオーラに気づかぬふりしてご機嫌を伺う母。
嫌われたくない。舌打ちされても、「クソッ」と呟かれても、未読スルーされても全然ムカつかない、むしろかわいいとは思っていたが、やっぱり寂しかった。「ママ」って、笑って走り寄る姿がオーバーラップしていた。
ところがいつの間にか、あっという間にスルリと彼の人生に飛び立った。ある日、何気なく送ったメッセージに、GOODマークがついた。
既読スルー常習犯のくせに、マークついた。二度見した。「ありがとう」と文字が返ってきた。二度見した。
あ、私だけ置いていかれている。彼がものすごいスピードで大人へ向かっている今、私だけ重力を感じているのかも。子どもの時間感覚に我々大人はついていけない。
天才物理学者のそれとは意味が違うかもしれないけれど、宇宙の広がりを感じると、人間の一生なんてほんの一瞬で、子育てなんて今となっては16分休符くらいの感覚だ。光速の真っ最中にいた時は、一日があんなに長かったのに。
この地球に、同じ時代に、私の元に生まれてきてくれた子どもたち3人よ、ありがとう。

母ゴコロ記事2022.09
どんぐりのうた
「ねぇ、今日久しぶりに体操着持たないで学校行く」。普段は私と話したくない空気を放っている息子が、私にそう言ったのには理由があった。
高校で部活に入ったものの、これまでとは全く違うレベルに愕然としていた息子。それでもなんとかがんばって、夏休みもほとんど毎日が部活だった。だから体操着を持たずに登校することは、テンション上がるウキウキな朝なのだ。
その気持ちを私にシェアしたかったのか。「よかったね」とだけ言ったが、「ママ、ママ」と何でも報告してくれた、あの頃の感覚が蘇った。
先日、公園で見つけたどんぐり。「まあるいのはクヌギだよ」そんな会話のできる期間は、もうとうに超えたのだと思っていたけれど、案外そうでもないのかもしれない。

お母さん業界新聞11月号







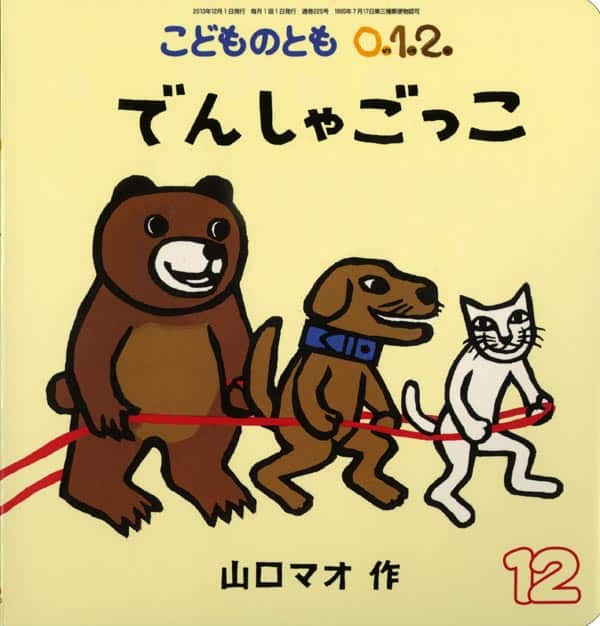

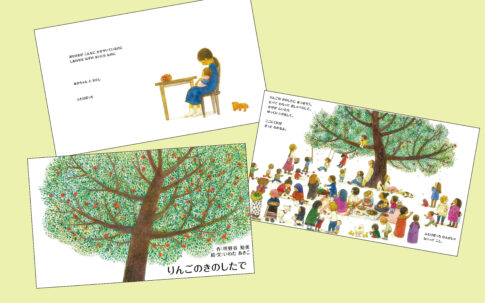


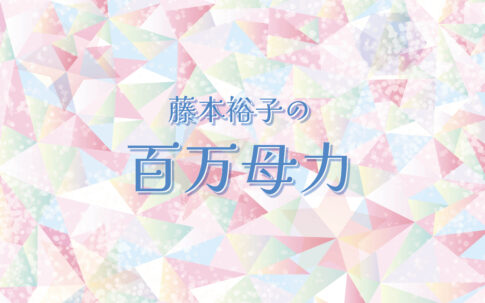



















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。