約2年前、思い返せば娘の心臓手術の直後、母ドラ1期生にぜひ受けてみて!とすすめられて手にした赤いドラッカーの本。
今思えば、まだ術後療養中で娘を見ながらの参加をよく決心したなと自分を褒めたい。が、決心したところで、すべてがうまくいくはずもなく、初回から欠席します、の連続。
まだ当時、前の時間に会議が入ることが多く、時計とにらめっこしながら過ごしていたことを思い出す。母ドラの日に限って、親子代わる代わるの体調不良だったり、予定が押して遅れて入ったり、後半は娘のお迎えで耳だけ参加…などなど、1ヶ月に1回、たった1時間半なのにフル参加できないもどかしさを抱えながらの2年間だった。
そして、まさかの最終回「母ドラ発表会」までも欠席せざるを得ない状況に、せめて「レポートをあげます!」と宣言してかれこれ2週間以上、ようやくここにたどり着いた。
宣言しておきながら、何をどうまとめようかと頭の片隅に置きながらもペンを持てず、進まずに来た。でも、よし書こう!と思えたのは、2年間画面を通して共に学んできた皆さんが自分の言葉で発表される姿を動画で見て、「ここでアウトプットしないとこの2年間の学びが流れていきそう」そんな焦りからだった。
私はどうだったかをこの2週間で改めて自分なりに考えてみたら、こういうことか!と母ドラが日常生活で活きていることに、終わった今だからこそ気づき、1つでも学んだことがあったと書きながら安堵している。
さて、その成果の1つ。
▶ 強みを基盤にする
この2年間で、仕事がかわり、新居への引っ越しに伴い、家族の生活パターンの変化が多く、毎日生活を回すのに精一杯だった。
特に夫に対しては「ちゃんとやって!もっとやって!自分で考えて!」と無意味に不機嫌になることも多く、つい最近まで自分にも嫌気がさしていた。
しかし、この母ドラ終了からの2週間で、「これが強みを生かすってことだ!」と思ったのは、夫が話し合ったわけでもなく、自分の仕事だと勝手に思っているであろう、洗濯、掃除、ゴミ出し、日用品のストック管理、娘のお風呂入れ、家計貯蓄管理全般等々、率先して担ってくれていることに気づいたからだ。
夫は普段、交代勤務で昼夜関係なく仕事に合わせる生活なので、家にいる時に、気づかないところでやってくれていたのを「当たり前でしょ、他にも子どもたちのケアもしてよ!」と感謝どころかさらに要求してしまっていたことに思い当たった。
周りを見回しても、こんなに出来る夫はいないかもしれないとさえ思えてきて、私が夫に求めていたのは、「親なんだからもっと子どもたちのことを一緒に考えて!」という思いだったのかもしれない。でも、仕事で家族との時間がずれがちな夫にとって、子どもたちのことを把握するのは実は難しいことだったのかもしれない。それを私だけやってる、と夫の不在時の子どもたちの様子を伝えることもなく、求めるだけ求めていた自分に気づいた。
そう気づいたら、ここだ!強みを生かすところ。
夫が率先してやってくれていることは遠慮なくお願いすればいい。これまでは子どもたちのケアは空気読んでやって!と求めていたことを、お散歩連れて行って、子どもたちとこれ買ってきて、◯時にお迎えねと具体的にお願いするようになった。すると、実は嫌がりもせずに子どもたちのこともやってくれることが分かった。
子どもたちにだってそう。
息子は家庭内外で、今日はパパだとか言って、夫不在時の娘の保護者代わりをしてくれる。娘もよくキッチンに来ては夕飯づくり、洗濯や買い物も手伝ってくれる。2人とも率先してやってくれるのは実は夫の姿を見て育っているからかもしれない。
周囲を見回して柔軟にというのは夫の強みではない。けれど自分の範囲の仕事は確実に効率よくできるのは強み。「強みを生かす」ことに気づいたら対応も代わり、負担も減り、心が軽くなった。
私が家庭全体のマネジメントをして、その中で家族がそれぞれにできることをやる。まさに母ドラ!
まずは2週間経っての気づき。
さて、夫の強みを基盤にした家庭内のマネジメントは一歩進んだが、私の強みは何だっけ…と新たに頭をひねる。日常生活に落とし込みながら母ドラをより深い学びに繋げていくのはまだまだこれからのことのようだ。
※TOPの画像は、母ドラ発表会の動画を観た後のテーブルの上。頭の中の散らかりようが目の前に表されてるな、と思わず撮った1枚。この景色が日常から少しずつでも減っていきますように。
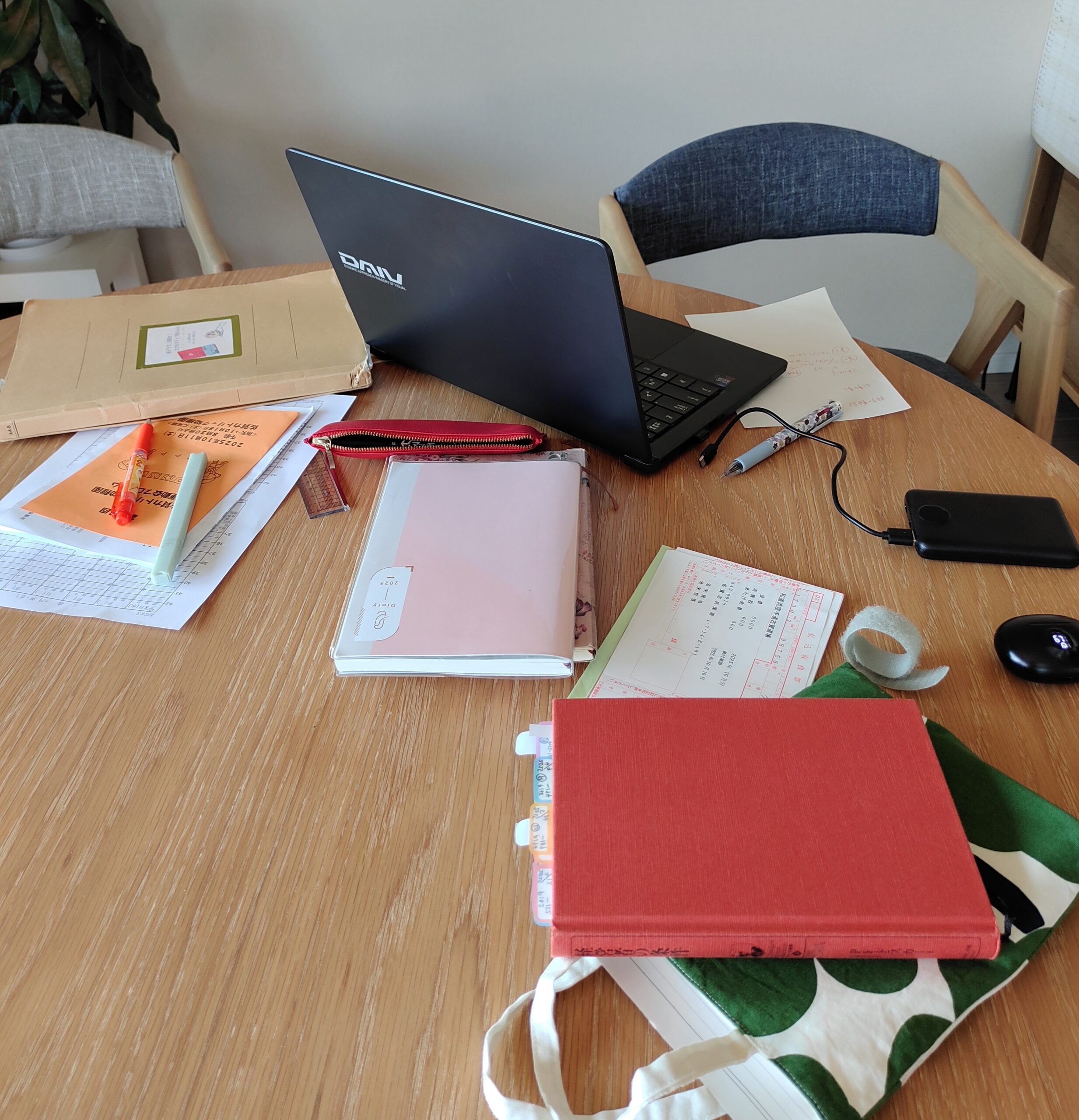



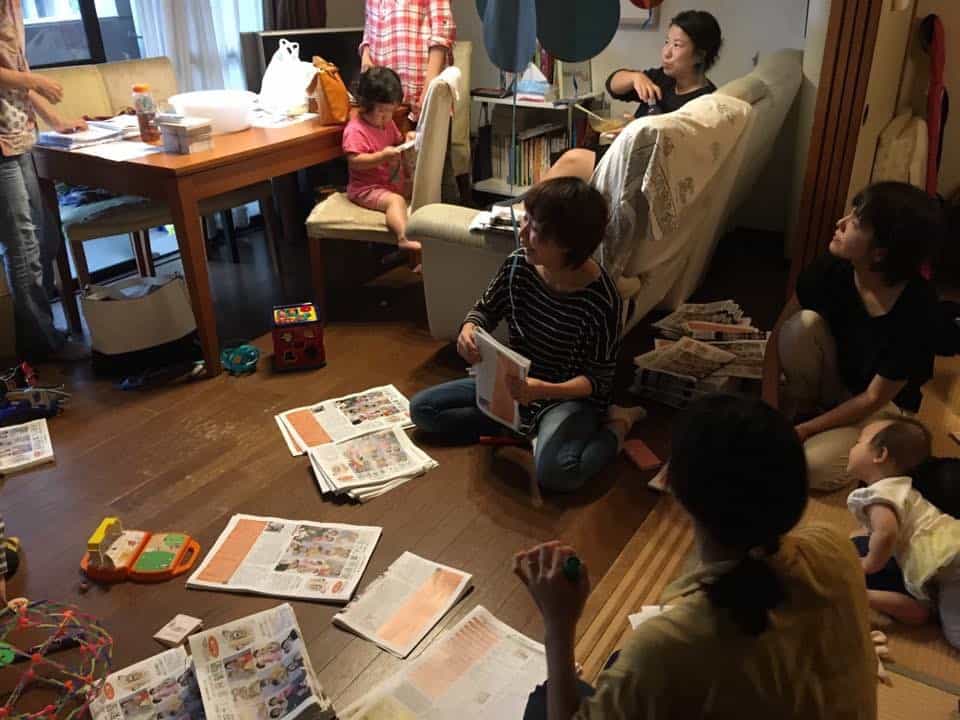



























レポートありがとう!
ちゃんと書けた池末さん、スゴイよ!
なんか読みながら泣けてきちゃったー。
安達さーん
とっても遅くなりました…。
毎月毎月、会の進行に段取りにフォローにとほんっとうにありがとう!
安達さんのサラッと言う言葉が納得だったり、グサリだったり、気づきだったり…日常でなかなかアウトプットできていないことを口に出して自分を見つめ直すいい機会だったよ。
今回の気づきで、学びを深めていく本番ってここからだなーって思ったところ。
ほんとほんと、レポートを書いた池末さんがすごい!!拍手です!!!
「娘を見ながらの参加をよく決心したなと自分を褒めたい」ぜひご自分を褒めまくってあげてくださいね^^
2年という短くない時間をご一緒できたことが嬉しかったです。
そして久留米でお会いできたことを鮮明に覚えています。
母ドラ繋がり、なかなか会えないけれど、これからも繋がって学んでいけたら嬉しいです。
これからも末永くよろしくお願いします。
そして私たち、お疲れ様でした!(もう乾杯したい気分です♬)
田久保さーん
ありがとうございます♡
毎回、田久保さんの実践エピソードや投稿記事、とっても楽しみでした!あ、今も楽しく読ませてもらってます。
田久保家の皆さんも影響していっているのも素敵だなって思いながら、お茶を差し入れするご主人にほっこりでした。
娘ちゃんにも久留米で会えたおかげで、あの子ね!って記事読みながらイメージできたり♪
また会える日を楽しみに!
ほんと
私たちお疲れさま〜
こちらこそありがとうございます♡
久留米でのあの一日が、より池末さんを近くに感じさせてくれるようになりました!
またぜひお会いしましょうね!!その時は乾杯しましょう☆彡
田久保さん
ぜひぜひ♡
その日を楽しみに、日常のあれやこれやを乗り越えましょう笑。
池末さん、ちゃんと報告記事をのこしたことが本当にすごい!!エライ!!
口で話すより、言葉に残すほうが私は難しかったので、実は母ドラに関しては一つも記事に残せてないのです。
母ドラを通して、家族のあり方を見つめなおすって、まさしくお母さん大学ならではの視点ですよね。
夫さんの強みを気づける視野の広さや、こうして粘り強くアウトプットにチャレンジするところが、池末さんの強みだな~と勝手に思いました。
脇門さん
お褒めいただけるだけで頑張った甲斐がありました〜!
皆さんお優しいから♡
私は考えを伝えるのがほんっとに苦手で、喋りながら着地点が行方不明ってよくあるので、時間かけて文章化する方がたぶん向いているんですよね。書きながら気づくことが多々ありました!自分にも言い聞かせながら。
2年間終了してようやく夫の強みに気づき、
今朝も夜中に帰ってきたのに、朝イチで息子を送り、帰宅したら洗濯物畳んで、掃除機かけて、風呂場とトイレの気になるところゴシゴシされてました。
そんな夫、本日お誕生日。朝イチでおめでとうって伝えたのでゴキゲンがよかったのかもですね!
母ドラありがとう〜!
池末さん、初めまして✨
岸珠恵と申します。
お母さん大学に最近入学したので母ドラが何か分からずに読み進めていたのですが、表現力の豊かさに心を奪われ最後まで一気に読んでしまいました!
忙しい毎日の中で、何気ない自分と家族の行動を振り返って分析するのって意識しないと中々できないことなのでとても素晴らしいし、私も真似してやってみたいと思いました✨インスピレーションをありがとうございます!
岸さん
はじめまして!
コメントありがとうございます♡
と、気づくのが遅くなり、今更のお返事ですみません!
記事を読んでいただけただけでもとっても嬉しいのに、
コメントまで♪
毎日バタバタとあっという間に過ぎていく時間が惜しくて
育児記録や自分と向き合う時間を取るためにお母さん大学生になったのに、子どもたちの成長とともに忙しさは加速していき…
でもこの場所があることで、ふとした時に覗いて、残したい出来事は書きに来て…と不真面目登校(投稿)ですが、
こうしてここで皆さんと交流できることもありがたいことです♡
今後ともよろしくお願いします!!