はじめに
少子化に歯止めがかからない日本。政府は2023年12月に「子ども未来戦略」を取りまとめ、その中で各種少子化対策(出産育児一時金の42万円から50万円への引き上げ、出産費用の見える化など)について効果検証を行うとともに、「2026年度を目途に、出産費用(正常分娩)の保険適用(現物給付化)の導入を含め、出産に関する支援等の更なる強化について検討を進める」方針を打ち出しました。
この方針を踏まえて厚生労働省・子ども家庭庁が出産関連検討会を設置し、4つのテーマに沿って議論を深めています。
(1) 周産期医療提供体制の確保
(2) 出産に係る妊婦の経済的負担の軽減
(3) 希望に応じた出産を行うための環境整備
(4) 妊娠期、産前・産後に関する支援策等
中でも(2)の「妊婦の経済的負担軽減」に関して、一般の傷病治療などと同じように、「出産費用を保険適用にする」という考え方があります。
それは、産科医療の処置やケアを全国一律に点数化するということです。出産は、必要な時間も必要なケアも、母子によって異なります。医療者には母子に対して総合的でかつ繊細な配慮が求められますが、それは一律に点数化が難しい性質のものです。
このように出産における特性を無視し、一律に点数化するのは、産婦および医療者に負担を増大させ、そのしわ寄せは弱者になりやすい母子にかかり、結果、妊娠・出産・子育てのQOLを低下させるのではないかと危惧しています。
そこで、長年、産む人の立場から出産に関わる活動をしてきた、「Umiのいえ」代表、お産を女性の手に取りもどすネットワークの齋藤麻紀子さんに、お話を聞きました。
(聞き手/藤本裕子、文/青柳真美)
お産の問題は、人生の根っこに響くこと

お産を女性の手に取りもどすネットワーク
齋藤麻紀子さん
NPO法人Umiのいえ代表。出産・子育て支援活動31年。産む人と医療者を結ぶネットワーク「REBORN」スタッフ(1995年~)から始まり、執筆・講座の企画運営・講演・ファシリテーターなど各地に出張。各地のお産を考える女性グループをネットワークし、国に提言を送る。
女性たちが望んでいるもの
出産はこれまで保険適用ではなく、自費払いで出産一時金を後からもらう形でしたね。妊娠・出産は「病気」ではないからです。
けれども国は、2026年よりお産の「保険適用化」と「無償化」に切り替えるよう審議を続け、準備に入っています。現段階においてその詳しい状況はわかりませんが、いずれにしても制度を変えるのであれば、当事者である女性たちの声を政策に活かしてほしいと思いました。
保険適用になると3割負担になるとか、無償化になれば、さらに家計には大変ありがたい。一見、「いいじゃん」って思えますね。でも、心配なこともあります。(この後に解説します)
金銭面も重要ですが、それ以上に女性たちが長年密かに望んできたのは「医療の質」です。
出産環境に何を望む?といっても、未経験の人にはピンとこない。そこで、出産経験者だからわかる観点で、意見を募集しました。
出産経験者たちの切実な声
2024年8月に実施したアンケートには、1か月で約4000人の出産経験者が声を上げてくれました。「人間らしい、産んでよかったと思える、お産がしたい」という切実な声が集まりました。続いて2025年7月に、「出産の保険適用化と無償化について」アンケートを行ったところ、10日間で約200人の回答が集まりました。
いろいろな気持ちが届きました。産科医療を受けて良かったこと、不快だったこと、助けられたこと、感動したことも、傷ついたこともたくさん。妊娠・出産・産後の感情はそのまま身体に残り、良くも悪くも、その後の子育てに響いていくことは、皆さん実感があることと思います。(※1参照)
帝王切開経験者にも聞いた
もう一つ、帝王切開経験者のアンケートも行い、まとめました。
今や4人に1人は帝王切開を経験しています。「命を救ってくださりありがとう」母も子も生きているのは、医療者の判断と機敏な対応のおかげ。一方で、「本当に切開する必要があったのか?」「非人間的な扱いだった」など、何年も拭えない苦しみを持つ人も大勢います。(※2参照)
保険適用になるとどうなる?
保険点数は、検査、投薬、診断に関わる諸々に加点されるようですが、出産においては、いったいどうやって点数をつけるのでしょう?
お産は人によってケースも違えば時間も読めません。長いお産、短いお産、車中で生まれてその後の処置だけのこともあるでしょう。産前の両親学級、助産師への相談、母乳育児のガイド、ケア、沐浴指導等諸々、助産師さんにしていただくケアは、それぞれ何点になるのでしょう。
もしもその一つひとつが低い点数だったとしたら、働き甲斐にも、経営にも関わってくると思います。ケアの質が向上するどころか、手を抜くしかなくなるかもしれません。
無償化になるとどうなる?
一方、「無償化」になったらどうなるか? それにはまず「標準のパッケージ」をつくるだろうと私は予想しています。妊娠中の健診から1か月健診までのフルセット。標準と定められたことは無料で、例外なことがあればその分が有料になるでしょう。
ここで肝心なのは、何が「標準」で何が「オプション」になるか、です。「マタニティクラス」「沐浴指導」「母乳教室」「助産師による相談外来」「授乳サポート」…その一つひとつが標準ではなく、有料のオプションになっていたらどうでしょう? その人に必要なことであっても、わざわざ受けないかもしれませんね。
なので、新たな制度をつくる時に、絶対欠かさないでほしいと思うことを、要望したわけです。
皆さんなら、「ここは欠かせない!」ということは何でしょう。豪華な食事やエステなどのサービスでしょうか? それとも、ずっと同じ助産師に手をつないでいてもらうことでしょうか。
無痛分娩は、よく知ってよく考えて選択を
無痛分娩を決める前に
国は無痛分娩を安全に受けられるような取り組みを進めています。東京都においては無痛分娩に補助金を出しました。他の自治体でも、無痛分娩に補助金を出す公約をしたら、票が集まると思っている政治家がいます。お金を出して痛みをとれば、女性は産んでくれるとでも思っているのでしょうか。
無痛分娩を取り入れたほうが集客が上がる。つまり産院経営的にも無痛分娩を扱うことが当たり前になってきています。産科医も日々ご努力されているとは思いますが、産科医が麻酔科医のように麻酔を扱うことの危惧も聞こえてきます。
また、日本の無痛分娩は日程を決めて行います。最近は38週どころか37週に人工的に誘発する施設も増えてきました。妊婦さんの身体と胎児の生まれる準備ができていないので、ある意味、無理やりな分娩です。そのことで親にも子にも、歪が起きているケースは大小さまざまあるようです。
お腹の赤ちゃんと対話をして
もちろん、1人目の分娩時、孤独と痛みと恐怖で「もうこりごりだ」という人が、次に無痛分娩を選ぶケースもあります。逆に、無痛分娩を経験してから、次は自然分娩を選択する人もいます。
赤ちゃんは自ら生まれる時に合図を送ってきます。時には、お母さんの身体を守るために、緊急搬送になるよう合図してくれる子もいます。赤ちゃんとお母さんのやりとりはお腹の中から始まっていて、すでに人であるし、人権もあるのです。
ですから無痛分娩を選ぶ人も、お腹の赤ちゃんと対話をして、その日を迎えることをおすすめします。
産む場所が集約化していく
出産にはもう一つ、「集約化」の問題があります。
全国的に今、クリニックや産科病棟の閉鎖が相次いでいます。住まいから1時間圏内に分娩施設がない地域は、ぐんぐんと広がっています。すると、大きな街の大きな病院に、県内から妊婦が集まるしかありません。住まいから遠く離れたところで、ベルトコンベアーに乗るような健診と出産になりかねないし、遠方から来る人には、計画出産をすすめられることでしょう。
助産師というお産のプロの力
この未来予想の中で、自分らしい出産をどうやって守っていくかが課題です。
なので、頼みの綱は、地域の開業助産師さんです。妊娠から産後まで、母親になっていく道を支えるプロがどの地域にもいますように。災害時に電気も水道も滞ったとしても、手だけで赤ちゃんを取り上げられる技が、未来の日本に残っていますように、これからも助産師さんを応援していきたいと思います。
お産の知恵と経験をつないで
最後になりますが、お母さん業界新聞を通して、当事者であるお母さんたちに、関心や意識を持ってもらうのが一番です。
産んだら終わりではなく、出産経験を活かし、次世代の女性たちのことを思って、どうぞお産の本音をお話してくださいね。医療者や行政へのフィードバックも大きな力となります。
お母さんたちみんなが先輩として、新米お母さんを助けていく仕組みと風土がどの地域にも必要だと思います。女から女へ、経験と知恵をつないでいけるよう、みんなが「ベテランの女」になったら、この国はまだまだ平和を保てると思います。
お母さん業界からウエーブを!
齋藤麻紀子さんとは、かれこれ25年のおつきあいになる。といっても一緒に何かをやったことはない。共通項といえば横浜で発信を続けていること。当時麻紀子さんがつくっていたミニコミ紙は『くまでつうしん』(現Umiのいえつうしん)、こちらは『トランタン新聞』(現お母さん業界新聞)だ。
あの頃は子育てサークルの全盛期。たくさんのサークルが地域で活動していた。四半世紀が過ぎた今、時代は変わり、ミニコミ紙も子育てサークルも消えていった。なので麻紀子さんとのもう一つの共通項は、今も活動を続けているということ。
昨年、麻紀子さんが弊社に来てくれた。お互い、よくは知らないのに、まるで同志のように仲間を感じた。麻紀子さんは「お産」を、私は「お母さんはスゴイ!」を、ブレずに伝えている。いや、正しくはしぶとく、もっといえば、性懲りもなくか…。
その麻紀子さんが、この度、国に提言をしたという。ここまでくるのはどんなに大変だったか。麻紀子さんや仲間たちが、未来のお母さんたちのために考えた提言なら、まずは、当事者であるお母さんたちに伝えなければ。そして、母なるすべての人は、その提言を心して読まなければならない。
少子化が止まらない国、子どもが生まれない社会になってしまったのは、私にも責任がある。だとしたら、せめてこれから生まれてくる赤ちゃんには、とびきりの笑顔であってほしい。
その笑顔を、その環境をつくれるのは、国ではない。唯一それができるのは、お母さんたちだと思うから。私たちお母さん業界新聞が、一番にこの提言をお母さんたちに届けます。
(藤本裕子)

正常出産の保険適用に関する提言書 ※1
お産を女性の手に取りもどすネットワーク
代表:齋藤麻紀子/佐治愛/山本ちかこ/上村聡美【1】陣痛促進剤より、助産師によるサポートの加点評価
陣痛促進剤など、積極的な医療介入に依存しない、専門的サポートによる自然なお産経過を支え、見守る助産師のケアを評価・加点対象としてください。
多くの女性たちが、陣痛促進剤の使用に伴う身体的・精神的負担を経験し、「できる限り自然なかたちで産みたい」と願っています。促進剤など積極的な医療介入に頼らず、自身の力と赤ちゃんのリズムを信じて進む出産は、安心感や満足度が高く、産後の回復も良好との声が多数ありました。こうした自然な陣痛の進行を支える助産師の知識と技術を、医療制度の中で正当に評価し、保険診療上でも加点されることを望む声が広く寄せられています。【2】産後の回復を促すケア・授乳指導の保険適用
乳腺炎予防や心身の回復につながる産後ケアや母乳マッサージ、授乳指導を保険診療に含めてください。
産後の母体ケア、とりわけ母乳ケアは多くの女性にとって不可欠です。助産師による母乳マッサージや身体ケアは、乳腺炎予防や母乳分泌の促進、さらには心のケアにもつながると高く評価されています。助産師の専門的な支援により、産後の不調が軽減され、母子ともに安心して育児に移行できたという声が多数寄せられました。自由診療では経済的負担が大きく、必要な人がケアを受けられない現状もあるため、保険診療の適用を強く求める声が多くあります。【3】赤ちゃんの世話に関する産後指導を保険適用に
オムツ替え・授乳・沐浴など、育児の基本的技術をすべての母親が安心して学べる機会を制度化し、保険でまかなってください。
赤ちゃんの世話に関する指導は、育児の不安軽減や産後うつ・虐待の予防に直結する重要なケアです。とくに初産の母親にとってオムツ替えや沐浴、授乳などの基本的な技術を習得することで、安心して育児を始める土台となります。家族の支援が得られないケースや核家族化が進む現代において、専門的な指導を受けられる機会は極めて重要です。従来の産後指導を制度の中に正当に位置づけ、すべての母親が受けられるよう保険診療に含めることが求められます。【4】両親学級・マタニティクラスの制度化
産前教育を妊婦健診の一部として標準実施し、不安軽減と出産・育児への主体的準備を支援してください。
出産や育児への理解と準備を深める産前教育は、妊婦の不安を軽減し、出産・育児に主体的に臨むための土台となる重要な機会です。SNS など不確かな情報に惑わされず、正確な知識を得るためにも、妊婦健診に組み込むかたちで標準的に提供されるべきです。産後うつ、虐待を防ぐうえでも効果があり、保険診療内で継続的・全国的に保障されることが求められています。【5】WHO コードに沿った母乳指導の保障
産前から一貫した母乳育児支援を制度的に位置づけ、適切な情報提供と継続的ケアを確保してください。
母乳育児は、赤ちゃんの免疫獲得や母子の愛着形成、母親の情緒安定にも寄与し、母子双方の健康を支える重要な営みです。多くの母親が「もっと早く知りたかった」「産前に適切な知識がほしかった」と語るように、WHO コードに沿った正確な母乳指導を産前から行うことは不可欠です。選択肢を尊重しながらも、母乳の意義と方法を理解する機会を保障することで、産後の不安や孤立、母乳育児の困難さを防ぐことにつながります。【6】助産師外来の保険適用
病院・クリニックなど医療機関における助産師による妊婦健診(助産師外来)を保険診療として位置づけ、対話的・継続的ケアを保障してください。
助産師による外来の保険適用を求める声が多く寄せられました。医師の診察は限られた時間で処置が中心となる一方、助産師は妊婦の心身に寄り添い、対話を通じて不安や変化を丁寧にくみとる機会となります。生活指導や心のケアも含めた助産師外来は、妊婦の安心感と自己肯定感を高め、産後のトラブル防止にも有効であり、制度として保障される必要があります。【7】医療介入を抑えた出産への加点評価
自然分娩に向けた努力と成果(非介入)を、加点評価により制度的に支援してください。
医療介入を抑えた出産は、母子の心身への負担が少なく、回復が早く、医療費の抑制にもつながります。自然なお産を支えるためには、助産師による専門的なケアや、時間をかけた丁寧な対応が必要であり、これは高い専門性と努力を要します。現在は医療介入が加点の対象となる仕組みが主流ですが、介入を避ける努力や実践もまた、同等に評価されるべきです。不要な介入を助⾧しない制度設計が求められます。【8】助産師による判断とケアの標準化
病院やクリニックで、医師の指示がなくとも、助産師の専門的判断によるケア提供を制度上明確に認め、現場での柔軟な対応を可能にしてください。
助産師は妊娠・出産・産後にわたり、女性に寄り添い、きめ細かなケアを提供できる専門職です。医師の指示がなければ対応できない制度では、適切なタイミングの支援が妨げられます。正常な経過においては助産師の判断で迅速に対応できる体制を整備し、安心と信頼に基づいた支援を保障すべきです。医師の⾧時間勤務問題解消にも寄与すると考えます。【9】継続的ケア(同一助産師による妊娠・出産)の評価
妊娠中から分娩まで、同じ助産師が担当する継続的ケアに対して保険上の加点評価を設けてください。
継続的ケアは母子の身体的・心理的負担を軽減し、産後の回復促進や医療費削減にも寄与します。そのためには、産む人を支える助産師の高い知識と判断力、継続的な支援が不可欠であり、それを正当に評価する仕組みが求められています。継続ケアの努力と成果を正当に評価し、保険診療上で加点すべきとの声が多数寄せられました。【10】助産院出産の保険適用
助産院出産を保険診療の対象とし、すべての女性が経済的負担なく場所を選べる環境を整備してください。
すべての女性が経済的に安心して出産場所を選べる制度を求める声が、多く寄せられました。助産院は健康な妊婦にとって安全かつ満足度の高い出産の場であり、不要な医療介入を避けることで医療費削減にもつながります。出産の多様性を尊重し、助産院の維持継続と選択肢の確保が必要です。【11】自宅出産(医療連携のある開業助産師による)への保険適用
安心・安全な環境での自宅出産を正当に評価し、病院出産と同等に保険適用としてください。
自宅出産は日本ではわずか0.2%と少数ですが、希望者は確実に存在します。自宅出産は安心・安全な環境であり、医療連携のもとで適切なケアが行われています。病院出産と同様に母子の安全を守る選択肢として、自宅出産も保険診療の対象にすべきです。多様な出産のあり方を尊重することが母子の幸福と少子化対策につながります。【12】嘱託医制度の見直しと新たな医療連携構築
助産院の開業・維持を妨げている嘱託医制度を廃止し、助産師と医師の対等な連携による地域医療体制を構築してください。
現在の嘱託医制度は、助産院の新設や継続を困難にし、妊婦の出産場所の選択肢を狭めています。誰もが安心して助産院で出産できる体制を整えるため、制度を見直し、助産師と医療機関が柔軟に連携できる新たな地域医療連携モデルの構築が必要です。【13】無保険者・社会的孤立者への出産支援の拡充
健康保険証を持たない人や社会的孤立下にある妊産婦に対する出産支援制度を整備し、安全・平等な出産環境を保障してください。
健康保険に加入できない人や保険証を持たない人が出産する際、現状では医療費の全額自己負担が障壁となり、受診の遅れや孤立出産のリスクが高まっています。出産はすべての命に関わる行為であり、誰もが安心して医療につながれる制度が必要です。保険証の有無にかかわらず、安全な妊娠・出産を保障する仕組みの整備が求められています。【14】多様な出産のかたちと寄り添うケアの保障
制度整備においては、医療モデルに偏重せず、多様な出産の形と助産師による寄り添い型ケアを継続的に守ることを求めます。
多くの女性が、画一的な医療介入ではなく、個別性と尊厳が保障された出産環境の継続と拡充を望んでいました。出産の保険適用化は歓迎されつつも、助産師の専門性や自然な分娩、産後ケアが切り捨てられることへの懸念は大きく存在します。制度設計には当事者の声を反映し、多様な出産の形を守る視点が求められています。
帝王切開出産に関する要望書 ※2
お産を女性の手に取りもどすネットワーク
帝王切開情報サイト「くもといっしょに」代表 細田恭子【1】 帝王切開についても十分な情報提供がなされることを望みます。
帝王切開で出産した女性の多くが、産前教育(両親学級・マタニティクラス)で帝王切開の情報を得られていません。あるいは「何かあった場合、帝王切開になります」といった中途半端な情報提供により、帝王切開を「自分には関係ないこと」と捉えたという声も多数あります。産前教育は保険診療になっても必ず実施してほしい。その際に、帝王切開についても十分な情報提供がされることを望みます。【2】より良い帝王切開のために、産前と産後の健診の充実を望みます。
予定帝王切開の場合、「前回経験しているから」との理由で、妊婦健診時に妊娠中から産後を見据えた身体づくりについてケアを受けられなかったという声が多数届いています。手術という出産を安心して迎えるために、予定帝王切開でも産む前からのケアが必要です。また帝王切開の産後の健診においても、母親が自分の身体をセルフケアできることを知り、安心して育児に移行できたという声もあります。十分な帝王切開の知識を持った助産師や理学療法士など含めた専門家によって責任をもって行われることを希望します。【3】妊娠中から担当助産師による継続ケアを望みます。
緊急事態が起きたとき、ひとりでは手術や麻酔の同意書や説明書などは落ち着いて読めません。妊娠中の経過や妊婦の背景を知っていてくれる信頼できる助産師がそばにいることが母子の身体的・心理的負担を軽減し、産後の回復促進や医療費削減にも寄与します。そのためにも、産む人を支える助産師の高い知識と判断力、継続的な支援が不可欠であり、それを正当に評価する仕組みが求められています。継続ケアの努力と成果を正当に評価し、保険診療上で加点してください。【4】妊婦が理解できていない段階で、一方的に医療行為をしないでほしい。
さまざまな処置があるが、それらは本当に必要なことなのか、ひとつひとつ、根拠ある説明が事前に必要です。体にメスが入り、傷が残ることを妊婦自身が理解できないまま同意書にサインを求められるケースも少なくありません。また、休日と重なるから…など納得しないまま帝王切開を勧められるという事例もあります。その後の夫婦関係、育児にも影響が出るからこそ、当事者主体の出産であることを希望します。【5】経腟分娩の場合と同様の産前産後の関わりを望みます。
「帝王切開は手術なので自分でできることはないと思っていた」という声が多数寄せられています。帝王切開のバースプラン作成・産後のバースレビュー・母子の絆作り・母乳育児の確立の工夫等、産前と産後のケアが経膣分娩と同様に、十分な知識を持った助産師によって責任をもって行われることで、自信を持って育児に移行できることから経膣分娩と同様の関わりを望みます。【6】帝王切開の手術中、助産師の寄り添いも必ず保険診療に入れてほしい。
手術中に手を握って励ましてくれた温かさや声を多くの当事者が覚えています。無機質な手術室で怖さと向き合う中、孤独ではなかったことがその後の育児にもつながっています。これまであった手術中の寄り添いが、保険適用になっても変わりなく得られることを望みます。【7】これからの妊娠出産の経験が幸せな体験となるために、寄り添いを評価する制度設計を望みます。
賛同団体一覧(2025.8.2 現在)※順不同
関西お産を語る会(大阪府)/NPO 法人Umi のいえ(神奈川県)/お産を語る会とりで(茨城県)/Birth For the Future@ぎふ(岐阜県)/神奈川の助産院に産声を(神奈川県)/産婆魂を無形文化遺産に!実行委員会/産前産後おやこのひろばWithMom(神奈川県)/一般社団法人ドゥーラシップジャパン(東京都)/一般社団法人母と子つながる笑顔プロジェクト(大阪府)/私たちのお産ダイアリー事務局 陽だまり(岡山県)/幸せなお産シェアリングの会(兵庫県)/任意団体うみのわ(愛知県)/産後ドゥーラ湘南(神奈川県)/Birth For the Future@ちた半島(愛知県)/むすびやのたね(沖縄県)/konety 合同会社(沖縄県)/育てよう!いのちの根っこ(東京都)/性教育団体「いのちの授業」ここいく(岐阜県)/一般社団法人ドゥーラステーションめぐる(愛知県・岐阜県)/お産からあたたかい社会までお母ちゃんの声、届けたいなキャラバン隊(京都府)/きょうとお産といのちの会(京都府)/家ウチ産みサロン(京都府)/たま~にお産を語る会(東京都)/お産ラボ(静岡県)/自宅出産を取り上げる助産師さんを応援し隊(広島県)/うまれることを語る会(広島県)/NPO 法人母の愛文化事業団(東京都)/母屋の和(和歌山県)/NPO 法人よしよし(静岡県)/NPO 法人母力向上委員会(静岡県)/特定非営利活動法人だっことおんぶの研究所(静岡県)/産巣日みんなで育つ会(大阪府)/自然出産を語る会(東京都)/NPO 法人バディプロジェクト(静岡県)/虹色たまご(静岡県)/お産とおっぱいのサークルかんがるーぐみ(静岡県)/三つ子の魂百まで 河州プロジェクト(大阪府)/いわてUmi のいえ(岩手県)/一般社団法人母と子つながる笑顔プロジェクト(大阪府)/妊娠・出産・子育て情報ネットワーク うみ・つき(熊本県)/コミュニティスペース“グランモッコビレッジ”(熊本県)
お産を女性の手に取りもどすネットワーク https://note.com/osanwomamorou
お母さん業界新聞10月号 緊急特集


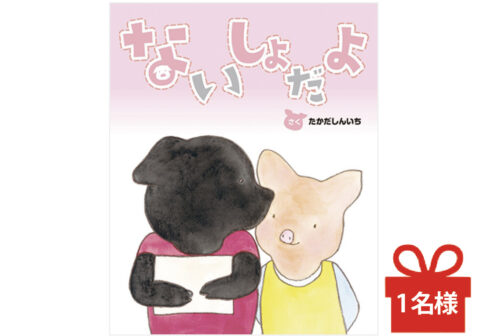


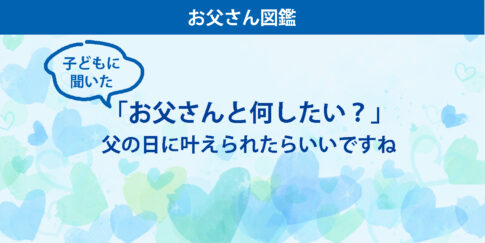

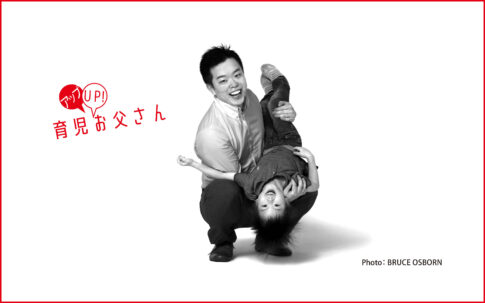
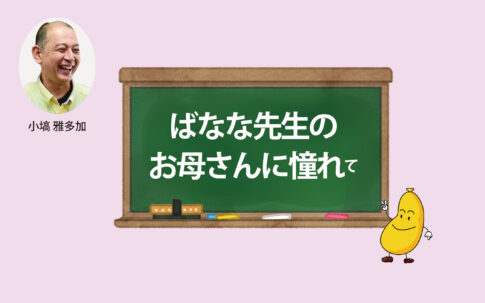
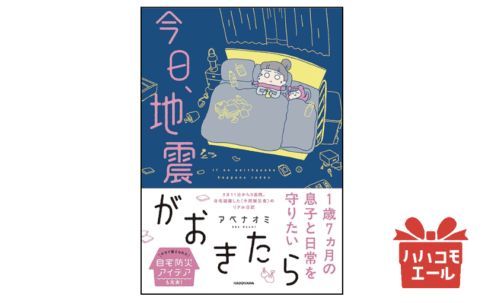

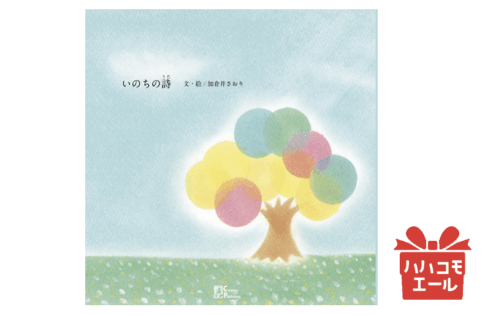




















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。