ただただ毎日が平穏なわけではないと感じた
7月30日の津波警報。
甥っ子たちが東京から遊びに来ていて、海沿いをドライブしながら水族館に行こうか!というところ。
10時前に携帯のサイレンと外から防災サイレンが鳴った。
横須賀に戻ってきて10年。
初めて聞いた音に驚いた。
テレビをつけると、日本地図が映し出され、注意報の黄色いラインが警報の赤いラインに変わったよ!と、子どもたちも気づいた様子。
わが家は少し高台で、東京湾の海が見える。
海から直線距離で1.5キロ程の場所に住んでいる。
この日は仕事を休んでいた。
子どもたちは手の届く所にいた。
夫は出張ですぐ帰って来れる距離でも、いざとなったら帰ってくることが出来ない。
もし、いつものように仕事に行っていたら?
こども園と学童に預けていたら?
1人で3人の子どもたちの安全を確保するためには?
そう考えたら冷静にいられるのか…。
この日は妹と甥っ子3人も一緒だったこともあり、落ち着いて情報を確認。
職場で情報をキャッチできない同僚へも連絡した。
あれこれ考えていたら、近くの保育園の分園(0歳1歳だけの施設)が、避難しているのが見えた。
10人ほどの先生が全員赤ちゃんをおんぶし、1人ずつ手を引いて1列になり歩いていた。
本園は高台にある。
警報が出た瞬間、すぐに用意をして出たのだろう。
そのくらい対応が早かった。
先生方の姿に鳥肌がたった。
もちろん、普段子どもたちがお世話になっているこども園、学童からも、状況連絡が入ってきていた。
第一波は3メートル予想。
わが家は海抜20メートル。
夫からも、第二波、第三波が怖いよ!
いつでも避難出来るように。と連絡が。
避難先は高台の幼稚園か、学童の本園!と決まっているが、その旨を確認し合う。
避難準備は、鞄にオムツ、ちょっとのお菓子、レジャーシートを入れ、おんぶ紐をセット。
充電できるものは充電し、1人1本水を持って、靴を履いて避難できるように用意した。
同じ町内でも海岸沿いは避難区域。
避難所にいる友人もいた。
幸い、津波到着は10センチで済んだし、
高台に避難することもなかった。
暑さもあり、避難か?それとも待機か?
避難区域じゃないけれど、判断の見極めは午後まで続いた。
電車が止まり、いつも必ず開いているスーパー、ご飯屋さん、病院、郵便局…が、どんどん閉まり、いつもは10分かからない道やガラガラの抜け道も大渋滞。
たまたま乾杯の日だったのもあり、あちこちオンラインが繋がり、いつも通りみんなの笑顔に救われたのも大きい。
翌朝、どんどん解除されていく警報、報道にさらにホッとしつつ。
帰宅困難だった、甥っ子たちを無事に駅まで送り届けられ安堵。
ごめんね、という気持ちと、一緒にいてくれてありがとうね。という気持ち。
よかった!よかった!の気持ちだけで終わるのではなく、この状況でどう判断するのか。を色んなバージョンで想像しないといけないのかも。
家からいつもの海を眺めながら、そう思ったのです。
今回感じたことは
暑さ問題
夏休み中だったこと
甥っ子たちが帰宅困難になり避難を共にしなくてはいけなかったこと
避難グッズは家族分より多く必要だったこと
海の近くに住んでいなくても、たまたま海の近くに旅行に来ていたことで津波警報のサイレンが鳴った、妹の携帯。
正解はその時々、準備の仕方も色々。
今回関係なかったなーではなくて、もしも自分があの場にいたらどうするだろう。を自分ごととして考えられたら、それは防災意識につながるのかもしれない!












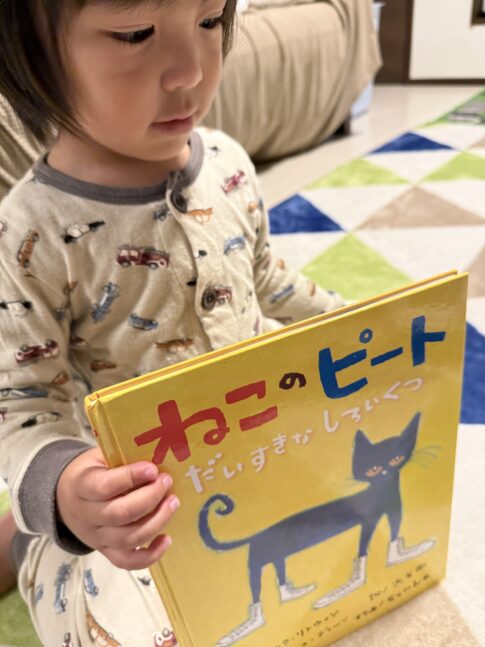



















岸さん
職場でも同じ建物内の高い位置の会議室に避難しました。
『夫からも、第二波、第三波が怖いよ!』
そうらしいです。
高台に車で避難していた同僚から、一波の到達が10センチと知って、みな車で帰り始めたそうです。
正しい知識と迅速な避難行動だと思いました。
横須賀市は、避難場所の開設など、とても迅速に情報展開しており、あっぱれでした。