試写会と取材のお話をいただいた際、タイトルを聞いて思い浮かべたのが、長女が最近「美しいと思う日本語」というテーマで書いた作文の一節でした。長女は、「中紅花(なかのくれない)」という色が好きと書いており、それは紅花だけで染めた明るい紅色だと言う。小学生の好きな色で到底出て来ないであろう色を挙げる、この感性にも触発されて、紅花をめぐる旅を見に行くことにしました。
紅花と言えば、紅花油しか知らなかったのを、紅花から染めることができると知ったのはつい最近のことでした。紅花は、シルクロードを通り日本に渡り、山形の地に行きつきました。戦争で一度は途絶えた紅花栽培。その種を守った人がいて、その種の子孫を播く人がいる。私は農業体験に行くことがあるのですが、一つのことを粛々と続けている生産者さんには、尊敬の念を覚えます。
紅花を摘むのは痛いのだそう。手で摘むのはもちろんのこと、腰に当たるだけでも痛いという。ベテラン紅花栽培農家の片桐いささんは事も無げに紅花を摘んでいく。紅花摘みが痛いと知るのは、出前授業で花摘みをする小学生を見てのこと。
私自身は、以前アパレル関係の仕事をしており、染色、堅牢度といった言葉に懐かしさを感じました。堅牢度とは、変色のしにくさや色落ちのしにくさのこと。紅花で染色したものは、色落ちが早く、日光に弱いそうです。ビジネスという視点では面倒にも思える紅花。その魅力を分かりやすく例えたのが、染色家の青木正明さん。
「料理もできないし、お金もかかる。でも、容姿がかわいくて、そばに置いておきたい女の子」 ― 紅花がそんな風に人を惹きつけるからこそ、紅花生産を残していきたい守人たちがいるのです。
山形は紅花生産の場であっても、染めるのは京都でした。
そして大阪の住吉大社には、商売繁盛と海路で運ぶ積荷の安全を祈り奉献された紅花燈籠があります。燈籠は紅花商人の栄華の広告塔のようなもので、かつては、その紅花ロードに紅花を供える習慣があったとか。
そんなお話も調査の上で、撮影しているものかと思えば、実は佐藤広一監督が染色家の青木さんに紅花にまつわる何かを調査してほしいと頼んで、知り得たことでした。
また、天然の紅染めに欠かせない烏梅の生産は、奈良県月ヶ瀬の中西さん親子が最後の砦です。
かつては、山形に大きな富をもたらした紅花生産も、今ではそれだけでは成り立たないそうです。山形市出羽の農家、長瀬正美さん・ひろこさんご夫妻は、紅花だけでなくトマト農家でもあります。そして、このままでは紅花文化を残せないと、取材を依頼したことから、この映画の製作は始まった聞き、通常とは逆の流れに驚きました。採算は取れるのか、効率や生産性をまず考えるこの世の中で、製作費を集めてまで映画作りをしていこうという熱意。
その熱意が監督に伝わり、山形、大阪、京都と奈良、普段はそれぞれの場を守る守人たちが紅花を通じて、つながっていく。紅花を共通点とする人たちが、映画をきっかけに縁がつながる。思いがあると、つながっていくものはつながっていく。そんなパワーを感じます。
山形美術館にある、江戸時代後期の絵師が残した紅花屏風には、紅花栽培から加工、流通までの過程が描かれています。その当時のその土地の人にとっては見慣れた風景、当たり前の景色、そういったものを残すことで、後世の人々に当時の様子が伝わり、追体験もできてしまう。表現するということの役割の大切さを感じずにはいられません。この映画もまた紅花の守人となるのでしょう。
これまでは知らなかった紅花の世界に触れ、青木さんの紅花の染色ワークショップなど、機会があれば行ってみたいと思いました。さて、私が興味を持つきっかけを作った長女は、私の土産話の何に興味を持つかと思ったら。「紅花、植えてみたい」と言う。染色に興味を示すと思ったけど、そこからか。
紅花のお話はまだ終わりではありません。新たに人を惹きつけて、物語はまだ続いていくのです。
詳しくは、「紅花の守人」公式HP:https://beni-moribito.com/
東京・ポレポレ東中野にて ロードショー他
大阪・10/8(土)から第七藝術劇場にて公開
全国順次公開

佐藤広一監督(左)と京都の天然色工房tezomeyaの染色家・青木正明氏(右)
福田有子記者の記事はこちらです。
いのちの継承-映画「紅花の守人 いのちを染める」






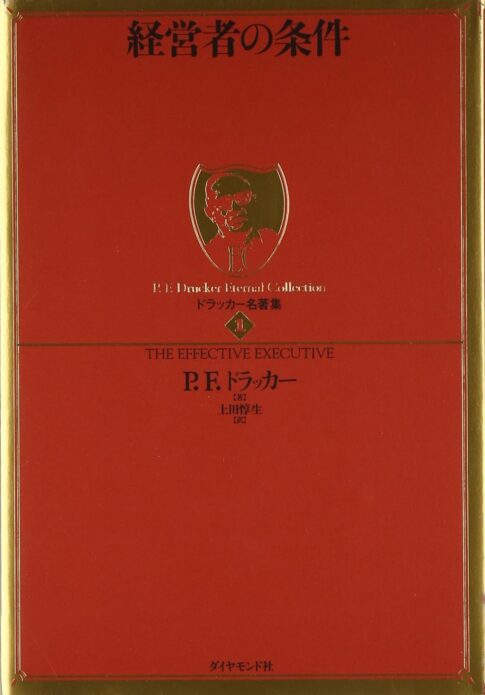






















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。