大阪市平野区平野宮町2-1-67

禰宜・藤江寛司さん
平安初期862年、平野郷の守護神として素戔嗚尊(すさのおのみこと)を勘請し、祇園社を創建したのが、抗全神社の始まりです。以後、熊野権現社、恵比寿社、稲荷社など多くの神様が祀られてきました。
平野は高野街道や平野川が通る交通の要所で、油、鍛冶、綿産業などの職人が集まり、それぞれ関わりのある神を連れてきたとされ、にぎやかな神社として栄えました。また、人の往来も盛んで、文化交流の拠点となり、国内唯一現存する連歌所があることでも知られています。早くから産業・商業が発展した都市だったため、近代以降の都市化は梅田や天王寺に任せ、平野は近世の面影を保ちながら穏やかに変化してきました。
大阪でも指折りの規模を誇る九町のだんじりが活躍する夏祭りが有名ですが、観光地というより地元の人々が長く受け継いできた伝統。今も行政の関与はほとんどなく、地域の誇りとして守られています。
今後は絵馬堂や会館を整え、地域に開かれた場とし、時代の変化を受け止めながら地域の要所として守っていきたいと考えています。
お母さん記者さんの「神様はみんなにいろんなことを頼まれて疲れているのでは?」という記事を読みました。ただお願いするだけでなく、双方向の関係を大切に考える感性は日本的だと感心しました。人々が神様を敬い、その力を強める。神様が「疲れているなら元気になってほしい」という気持ちこそ祭りの原点です。
本来、神事とは神様の心を和らげ楽しんでいただく奉納行事のこと。そこに自然と地域への思いがあふれ、守られているのだと実感します。
(取材/宇賀佐智子)

樹齢850年のクスノキが迎える
お母さん業界新聞10月号 子育て× 神社・お寺プロジェクト

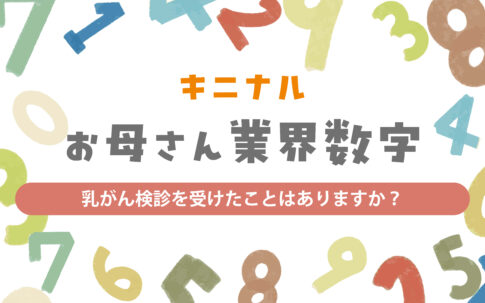






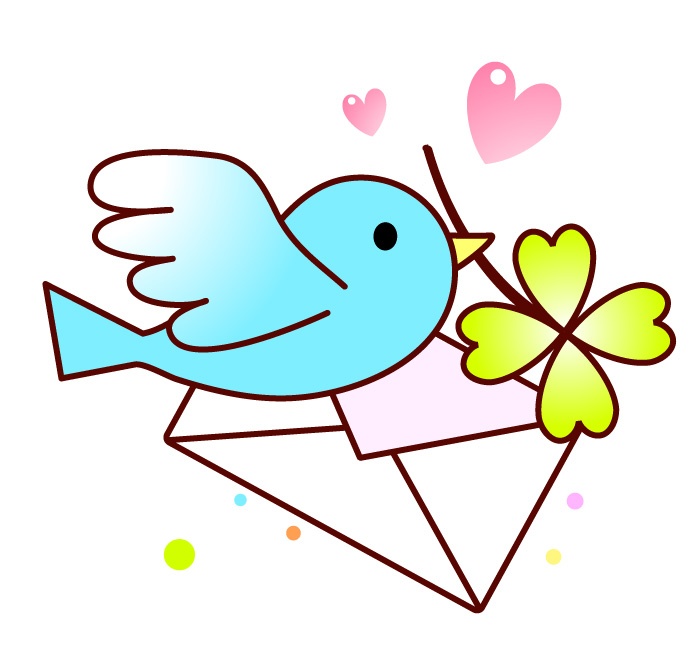
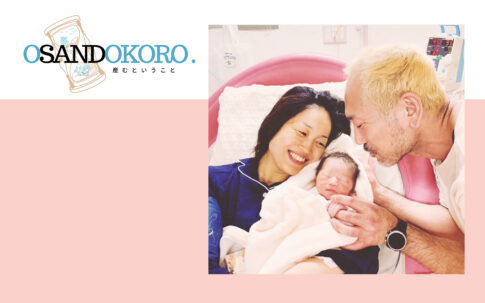
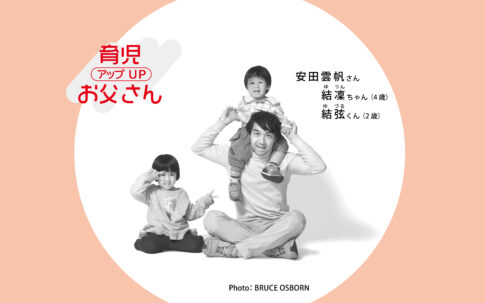

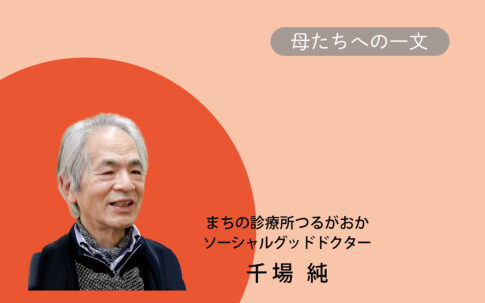



















コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。