ご報告が遅くなりましたが、先週行った折々おしゃべり会 in 筑前町のご報告です☆
今回の折々おしゃべり会は、いつもと全く違う形態と内容と雰囲気でした。
なぜなら・・・大阪のお母さん大学生、みっこさんこと池田美智子さんのご参加!!
そして、行政関係者が5名参加してくださったからです。
直前に参加キャンセルが数名でしたが、参加されたお母さんたちは11名。
こども5名。
それプラス行政関係者が5名。
いつもより人数が多いとのことが事前からわかっていたので、
いつも場所を貸してくださる心ゆるりさんのご配慮で、二間続きの和室を開放して使わせて頂きました。
なぜ、行政の方が参加されることになったかというと・・・
今月号の町の広報に
【ちくぜん助け合いの会 みんなで創るお互い様の社会】
-筑前町における、地域の支え合いを一緒に考え、仕組み作りをしてくださる住民の方を募集しますー
との広報が載っており、私がそれに手を挙げたからです。
ずっと前からお母さん大学で、そして、各地で行われている折々おしゃべり会がやっていることは
まさにこのことだと思うし、私たちだけでやっていくには限界があり、完璧なものではありません。
より多くの方と繋がり、より多くの方にこの新聞が届くためには、
行政の力を借りることも、借りる時も必要だと常々思っていたので、
お互いに良い関係で活動がシェアできたらとの想いで、このプロジェクトに手を挙げました。
すると、その折り込み会がどんなものか、見せて頂きたいとのことで、今回参加されることになったという経緯です。
ただ、行政関係者だろうが町議員さんだろうが、立場に上下はなく、
皆さんが同じフラットな立ち位置で、忌憚なく意見交換がしたいと思い、
行政の方にも一緒に輪の中に入ってもらい、新聞の折り込みをして頂きました。

今回、いつも参加してくれる筑前町のメンバーの他に、
小郡から、筑紫野から、久留米から・・・と遠方からの参加者が半分でした。
(以前、久留米の折り込みで出逢ったお母さんが、1度しか会ってないにも関わらず
「美和子さんに会いたいので、行きます!」と連絡して、参加してくれた方も♪)
初めましての方も、久しぶりの方もたくさんいましたが、
いつもと違う雰囲気ながらも、新聞を折って、ひとつの輪で、ひとつの作業をすることにより、
自然と距離は近くなり、自然に色んな話ができました。

・「子育て支援センターはあっても、行けない・行きたくない」そんなお母さんの生の声。
・国や地方自治体がリードして行うサービス(公助)には限界が来ており、
これからは、地域の住人同士が助け合う自助・共助の時代になっていく。
その仕組みをどうやって作っていくかが課題だとの話。
・行政任せの団体は潰れていく。
自分たちので力で立ち上がり、自分たちでどんどん力をつけ、高め合っていく団体は生き残っていくという話。
・30年前から子育ての時代背景をずっと見てきた。(みっこさんの話)
そこから見える社会の在り方が、親や育児に影響している。
「お母さんは支援されるだけの存在ではない。自ら立ち上がってアクションしていく力があるんだよ」
という、藤本さんの言葉を紹介した私の補足説明もしてくださいました。
・「お母さん大学とはこういう場所」という説明を、自分の記事を読みながら、
そこにコメントをしてくれたみっこさんのコメントを読みながら、説明してくれた、伊藤ちゃん。

それを嬉しそうに聴く、みっこさん。

・助けを求めたいけど、求められないお母さんたちがいる現状を語ってくれる、心ゆるりスタッフ。

・子育て支援サービスが充実すればするほど、
「やってもらう」「何かしてもらう」ことが当たり前になり、それが今度は
「やってもらえない」「こうじゃない・ああじゃない」と不満に変わる。
・実家が遠い、または、近くにあっても様々な事情で実家を頼れない母親たち。
地域にいる元気なお年寄りの方たちと、子育て世帯をどう繋いでいくのかという課題。
ただし、たとえそこが繋がったとしても、今の子育ての考え方と昔の考え方(価値観)の差やギャップにより、
何気なく言われた一言で、今子育てをしているお母さんたちが傷つく・心を閉ざしてしまうという事例もあり、
その差にどう折り合いをつけていくのかという課題。
・この折々おしゃべり会は、私たちお母さんたちが主体となって動いて開催しているということや
そもそも、そんな会があったなんて知らないと言う行政。
また、行政内で知っている課があるにも関わらず、他の課と連携できていなかったり、
必要なお母さん方に届いていかないという課題。
まだまだ知らない地域資源がたくさんあるにも関わらず、そこが繋がっていくというのはとても難しい壁。
「共助」を実現していくには、どうしたらいいのかを、みんなで考える時間でした。
『壁は、壊すためにあるんじゃない』
と言った行政の方の言葉も印象的で、納得するものでした。
そして、最後の30分で、「ちくぜん助け合いの会」とはどういうプロジェクトなのかを説明してくださいました。

この折り込み会が、今(まで)参加してくださっているお母さんたちの
居場所に
楽しい場所に
安心できる場所に
なっていることは間違いありません。
ただ、それだけでいい。
と思う自分。
でも、もっともっと孤立して、しんどい想いをしているお母さんに来てもらえるような場所にしていきたい
と思う自分。
だって、かつては私もそうだったから。
地域のいろ~んな人に助けてもらって、2人の息子を育ててもらったから。
「ひとりじゃないよ」「何か困ったことがあったら頼ってね」
そんな、顔の見える・血の通った温かいものが、この場所にはあります。
そのためには、【安心・信頼できる】色んな力と繋がりを結集して、
「寄ってたかって」
「総がかりで」
「みんなで」
子育てしていきたいと思うのです。
そのためには・・・どうしたらいいのでしょう?
この折々おしゃべり会の意味と存在意義を、改めて感じた時間でした。


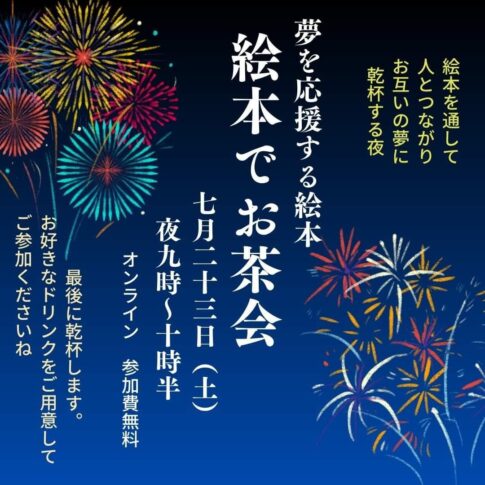








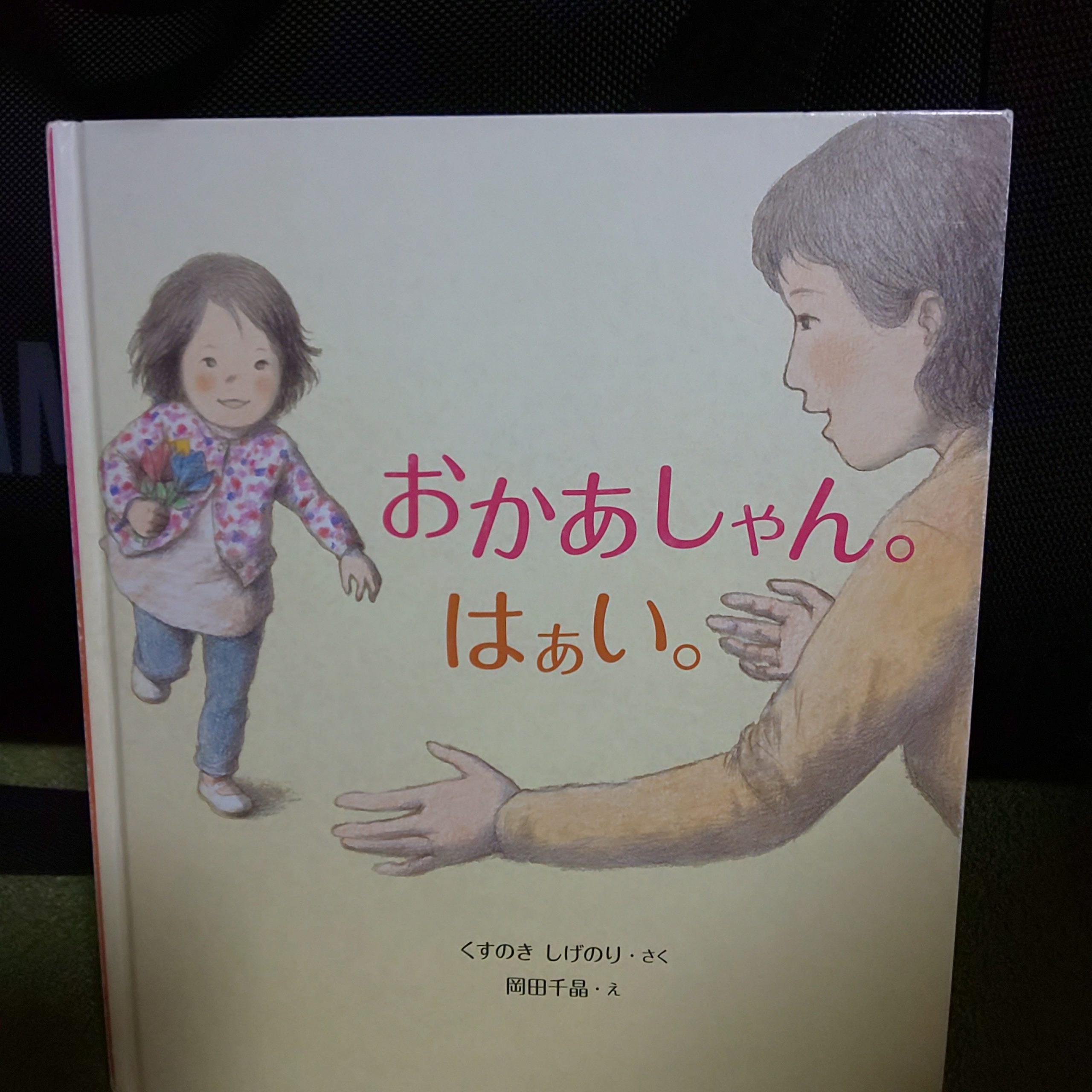




















記事を読みながら、初参加の折々お喋り会の興奮が蘇ってきます。
色々とお世話になり充実した1日を味わいました。
行政の方や議員さんが興味を持ってくださったことは前進だと思いました。
できる範囲で地道に長続きできるような知恵と工夫が必要だと感じました。
場所を提供してくださる「心ゆるり」さん、そこは1件家の居心地の良さがありました。
話しやすい雰囲気になり、意見交換も皆さん臆することなく発言されていたのが印象的でした。
伊藤さんのスマホ読み上げに、私はその時々に感じたことをコメントしてはいても、当たり前ですが
忘れていたのでサプライズに感じて嬉し恥ずかしでした。
私はまだ日常に戻れずにいます。
みっこさんがいてくださったからの、あんなに色んな話が深まっていったのだと思います。
本当にありがとうございました!
そして、個人的には楽しくて嬉しくて仕方のない時間でした。
昨年秋から細々と始めた会が、こんなあったかい、そして有意義な会になっていることに喜びでいっぱいでした!
心ゆるりさんの雰囲気がいいでしょう♪
やっぱり畳がいいな、と思います。
突然すみませんでした…(^^;
あの日は私の中で忘れられない一日です。
かけていただいた大切な言葉は
忘れてしまわないように心と紙に書いて
見て思い出しています。
長旅お疲れさまでした。
通常運転に戻り
好きなことをして過ごす毎日となりますように。
みわちゃんレポートありがとう♪
とても分かりやすくて
あの日の記憶が甦るよ~
あの広報紙の小さな募集欄を見て、すぐさま手をあげ
行政の方が折り込み会に来てくれるまでに
繋いだみわちゃんのパワーに圧巻です。
その思いを繋げていけるように
何かできることがあれば
私の小さなパワーでよければ使ってね!
写真も撮ってくれてありがとう…(照)
毎日お疲れさま
ゆっくり休めますように☆
深夜に眠れずに
久々に訪れたお母さん大学のサイト
やっぱりいいなぁと思ってしまったよ
たくさんの人に知ってほしい!ヽ(´▽`)
ゆうちゃん、ありがとう!
深夜に登校できるのが、このお母さん大学の良さだよね!
遅刻も早退もないしね(笑)
いつもゆうちゃんには助けられてるよ♪
小さな力を結集して、子育てしやすい町になったらいいよね。
お母さんたちが生き生きと、楽しく、自分たちで繋がり合って子育てする&地域の困りごとを解決する
→それが何よりの「地方創生」だし、「総活躍社会」だと私は思ってるよ。
何も、外で男性並みに働くだけが、「活躍」ではない!!!
地方再生そして創生の言葉があちらこちらで目にする時代です。
中央集権で高度成長期を乗り切って経済発展をした団塊前後世代の私が行政の方の言葉を聞き
伝えたいことが出てきました。
豊かさを満喫した世代はバブル世代だったこと。
その後は成熟世代と言われ、飽和状態の中で何をしたらいいのかわからない状態にあったこと。
そして日本社会も同じように何から手を付けたらいいのかさえ分からない状態になっているのです。
中央政権に頼る時代はとっくに終っているのです。
だからこそ、個人レベルで自分が何をするのかどうしたいのかを考えながら仲間を見つけ
できることから始める時代になっているということだと実感しています。
みっこさん。コメントをいつものように残してくださる日常に戻られたのですね。
ここで、またやりとりができること、楽しみにしいています♪
>中央政権に頼る時代はとっくに終っているのです。
なるほど!!
地方から、個人から、民間から、憶することなく声を上げ続けたい!と思います。
それぞれに良い活動をしている地域資源があったとしても、
そこが分断されていてはもったいないし、残念だと思うので、
このようなプロジェクトで地域の方たちと繋がり、
お互いにプラスになるような方向でやっていきたいなと、ワクワクしています♪